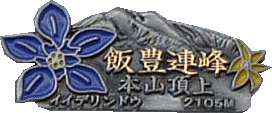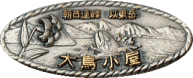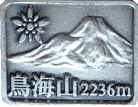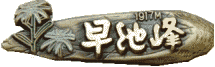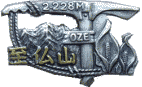|
大朝日岳
(朝日連峰)
(1870m)
朝日鉱泉
|
Y字型雪渓、ヒメサユリ |
大鳥池から縦走して、朝日鉱泉に下山しました。降りてからの生ビールは格別おいしかったです。朝日鉱泉は、「朝日連峰山だより」を読んで、いつか泊まりたいと思っていた宿です。バッジには朝日鉱泉側から見えるY字型雪渓が描かれていました。(2018年8月19日、山形県) |
 |
大朝日岳
(1870m)
タキタロウ山荘 |
ピッケル、ヒメサユリ |
以東岳から大朝日岳への稜線は、のびやかでした。前回、大朝日岳から狐穴小屋までは歩いていました。ピラミダルな大朝日岳は変わっていませんでした。銀玉水がおいしかったことを思いだし持ち帰りました。(2018年8月17日、山形県) |
 |
以東岳
(1771m)
タキタロウ山荘 |
大鳥池、ヒメサユリ |
2回目の大鳥小屋は、タキタロウ山荘として名前が変わっていました。1回目はテント泊で雨のため以東岳に登らず帰りました。今回は小屋泊まりです。以東岳に登ると、はるか向こうに大朝日岳が見えました。(2018年8月17日、山形県) |

|
会津駒ヶ岳
(2132m)
駒の小屋
|
ハクサンコザクラ、駒の小屋 |
駒の大池は青く澄んで、尾瀬燧ヶ岳も近くに見ることができました。駒ヶ岳から中門岳までオオシラビソが点在する草原を歩くと、ハクサンコザクラのお花畑もありました。(2012年8月19日、福島県) |
 |
会津駒ヶ岳
(2132m)
檜枝岐
|
ハクサンコザクラ |
檜枝岐から尾瀬には何度か行きましたが、檜枝岐から登れる会津駒はまだの時、ふもとの売店で買ったバッジです。いつか登ろうと思って買いました。(2012年8月19日、福島県) |
 |
飯豊山
(2105m)
門内小屋
|
イイデリンドウ |
梶川尾根から登りました。急坂の連続で、門内小屋にやっとで到着しました。雪渓の氷で冷えたビールといっしょに買ったバッジです。好天の翌朝、管理人さんは、久々に外で朝食を食べる気になったと言っていました。(2009年8月15日、山形県) |
 |
飯豊山
(2105m)
本山小屋
|
ヒメサユリ |
飯豊連峰縦走は、好天に恵まれました。もう少し時期が早ければ、ピンクのヒメサユリが見られるようです。(2009年8月17日、福島県) |
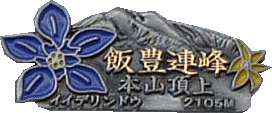
|
飯豊山
(2105m)
本山小屋
|
イイデリンドウ・ミヤマキンポウゲ |
イイデリンドウは、つぼみが多かったですが、見ることができました。8月中旬以降は、お花畑も秋のよそおいでした。(2009年8月17日、福島県) |
 |
飯豊山
(2105m)
三国小屋
|
イイデリンドウ・オコジョ |
本山から三国小山までは、岩稜が多く、山岳信仰の名残りを示す地名も多くありました。三国小屋ではゆっくりすることができました。(2009年8月17日、福島県) |

|
飯豊山
(2105m)
梅花皮小屋
|
小屋 |
梅花皮(かいらぎ)小屋と読みます。飯豊連峰の稜線からは、石転びの雪渓がよく見えました。(2009年8月16日、福島県) |
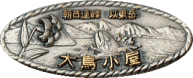 |
以東岳
(1771m)
大鳥小屋
|
タキタロウ
ミヤマウスユキソウ |
朝日連峰といえば大鳥池。謎の怪魚タキタロウで有名です。泡滝ダムから入りました。原生林の中に大鳥池がありました。しかし、雨の連日。テントに泊まって帰りました。(2002 年8月11日、山形県) |
 |
鳥海山
(2237m)
五合目矢島口 |
チングルマ? |
秋田県の祓川キャンプ場で泊まりました。翌日は快晴。朝日を受けた鳥海山はきれいでした。バッチは、祓川ヒュッテまたは朝日荘で購入しました。(1999年7月28日、秋田県) |
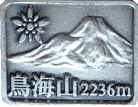 |
鳥海山
(2237m)
山頂大物忌神社 |
チョウカイフスマ |
チョウカイフスマは、鳥海山を代表する高山植物です。白い花ですが、登った当時見逃してしまいました。鳥海湖のほとりで見た黄色いニッコウキスゲが印象的でした。(1999年7月28日、秋田県) |
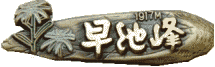 |
早池峰
(1914m)
早池峰神社付近の売店 |
ハヤチネウスユキソウ |
早池峰の花は、なんと言ってもハヤチネウスユキソウです。雨の中、岩陰にこの花を見つけました。8月になって2回目に登ると、もうこのウスユキソウの花期は終わっていました。(1999年7月24日、岩手県) |
 |
七時雨山
(1060m)
ネットで購入 |
牧場、ウシ |
七時雨山は、天気の変化が大きい山と聞きました。登り口は牧場の牧歌的な山でした。山頂からは、姫神山、早池峰、岩手山、八幡平が見えました。(1999年7月25日、岩手県) |
 |
八幡平
(1613m)
アスピーデライン頂上売店 |
コマクサ・ザイル |
岩手山を望みながら、大深岳から森の中を歩きました。山頂付近は、なだらかでアオモリトドマツ(オオシラビソ)の原生林でした。山頂近くまで、アスピーデラインが来ています。そこの売店でバッジを購入しました。(1999年8月10日、岩手県) |
 |
燧ケ岳
(2356m)
下田代 |
ミズバショウ・ピッケル・ザイル |
尾瀬には、徒歩で入りました。しかし、燧ケ岳のふもとの下田代は町のようでした。ミズバショウを見るためには、雪溶け後の春先に行かなければなりません。福島県側桧枝岐には、「夏の思い出」の詩碑がありました。(1994年10月9日、福島県) |

|
至仏山
(2228m)
山ノ鼻 |
ミズバショウ・ピッケル・ザイル |
1回目は鳩待峠から登りました。2回目のときは、山ノ鼻コースから登りました。高山植物は2回目のコースのほうがあるようです。ピンクのタカネナデシコが印象的でした。(1994年10月8日、群馬県) |
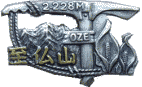 |
至仏山
(2228m)
下田代 |
ミズバショウ・ピッケル・ザイル |
一面の湿原には感動しました。尾瀬はニッコウキスゲの群落も見事です。しかし、「夏の思い出」の歌の影響は大きく、バッジの花はどれもミズバショウでした。(1994年10月8日、群馬県) |